|
 |

アジアフォーカス 福岡国際映画祭 2013
< Focus on Asia-Fukuoka International Film Festival 2013 > |
| [開催期間] |
2013年9月13日(金)~23日(月) |
| [会場] |
キャナルシティ博多 |
| [URL] |
http://www.focus-on-asia.com |
「現在注目を集めている優れたアジア映画を世界に紹介していく」「映画を通して、市民のアジアに対する理解を深める」「映画を通して、市民レベルでの文化交流、国際交流を推進していく」「映画界の新しい才能の発見と育成」を目的とした映画祭。毎年、9月に福岡で行われている。
「福岡アジア文化賞受賞記念上映&シンポジウム」ではアピチャーポーン・ウィーラセータクン監督が来福し、福岡アジア文化賞 芸術・文化賞を受賞したのを記念してシンポジウムが行われる。また、同監督の作品が四本上映される。 |

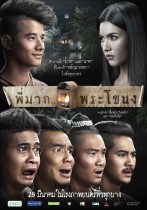 |
| 「死者の村からこんにちは(ピー・マーク プラカノーン)」 |
| <上映されるタイ映画> |
| [邦題] |
死者の村からこんにちは(ピー・マーク プラカノーン) |
| [英題] |
Pee Mak Phra Kanong |
| [原題] |
พี่มาก..พระโขนง |
| [製作年] |
2013年 |
| [監督] |
バンチョン・ピサンタナクーン<Banjong Pisanthanakun/บรรจง ปิสัญธนะกูล> |
| [出演者] |
マーリオー・マオラー<Mario Maurer/มาริโอ้ เมาเร่อ>、ダーウィカー・ホーネー(マイ)<Davika
Hoorne(Mai)/ดาวิกา โฮร์เน่(ใหม่)>、ポンサトーン・チョンウィラート<พงศธร จงวิลาส>、ナッタポン・チャートポン<ณัฏฐพงษ์
ชาติพงศ์>、アッタルット・コンラーシー<อัฒรุต คงราศรี>、カンタパン・プームプーンパチャラスック<กันตพัฒน์
สีดา>、ウィワン・コンラーシー<วิวัฒน์ คงราศรี> |
2013年に公開され大ヒット。タイ映画興行史上最高の記録を樹立した作品。ホラー・コメディー。事実だと信じる人も多いと言われる、タイの有名なホラー伝説「メー・ナーク・プラカノーン」の2013年版。マーク(マーリオー・マオラー)は徴兵され、身重の妻ナーク(マイ)を家に残して戦場へと赴く。しかし、マークが戦場にいる間にナークは死んでしまい、マークはそのことを知らない。負傷したマークは、戦友らと共にプラカノーンの自宅へと戻って来る。そこには、夫を愛するあまり、死しても幽霊となって夫を待つ妻と赤ん坊がいた。だが、マークはそのことを知らない。マークとナークは喜びの再会を果たし、マークは戦友達をしばらくの間離れに泊めることにした。マークらが村へ行くと、どうも知人たちの様子がおかしい。妻のナークが幽霊だというのだ。・・・というストーリー。
GTH社作品。この題材は、過去に何度も映画化、TVドラマ化、舞台化がされている。タイトルが「メー・ナーク」ではなく「ピー・マーク」になっていることからも想像がつくが、今回の主役はナークではなくマークだ。
この作品は、ひとことでいうととてもおもしろくて楽しめる作品となっている。最初から最後まで劇場内は笑いっぱなしだ。しかも、その笑いの取り方は、タイ映画お得意の下品なドタバタ・コメディーではない。これなら、タイ以外の国でも受けるに違いない。特に作品の冒頭では、編集の妙で笑わせてくれる。こういう作品は珍しい。もちろん、いい演出があったからこそ編集で笑わすことができたのだが。演出、脚本、撮影、編集がすばらしい。
そして、出演者も良かった。特に良かったのは、マークの戦友達を演じた助演の四人(ポンサトーン・チョンウィラート、ナッタポン・チャートポン、アッタルット・コンラーシー、カンタパン・プームプーンパチャラスック)。見事に笑いを取っている。そして、愛妻家である主演のマークを演じたマーリオー・マオラーが、かわいらしかった。彼、以前に比べて演技がうまくなったと思う。
ナーク役の女優マイは、「ファザーランド(Fatherland)」<2012年>に次いで映画は二本目の出演。TV出演は2010年からある。TVドラマ「ガオ・カーム・テープ(เงากามเทพ)」では主題歌も歌っている。今作公開年には21歳になる若手だ。ちょっと難しい役だったと思うが、怖さの中にかわいらしさを交え無難にこなしていた。
冒頭の戦闘シーンはかなり迫力があった。だが、主人公たちが体に弾丸を受けているのに、(コメディー・シーンではないにもかかわらず)劇場内では笑いが湧き上がるという珍しい現象が起こった。それだけ、冒頭から観客を笑わせていたということなのだが。観客が笑いたくなる気持ちは分かる。残念だったのは、有名なマナオのシーン。あまりにもあっさりと流してしまっている。これだけすごい作品なのだから、何か工夫して見せてくれればより盛り上がったと思うのだが。
作品は、正統派「メー・ナーク・プラカノーン」とはちょっと違った結末を迎える。こういう終わり方をする「メー・ナーク・プラカノーン」は初めて観た。また、本編終了後のエンド・ロール中に後日談が展開するのだが、これがまた傑作だった。
この作品の中には、どうしても外国語に訳すことができないことばや習慣、言い伝え、歴史を知らない外国人には笑えない部分もあるが、それでも十分に楽しむことができる内容となっている。とにかく、楽しい作品に仕上がっている。
挿入歌「ヤーク・ユット・ウェラー(อยากหยุดเวลา)」がとてもいい。この曲はオリジナルではなく、元歌は1991年のサランヤー・ソンサルームサワット(Saranya Songsermsawad/ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์)のものだとのこと。
バンチョン・ピサンタナクーン監督は、日本でも公開された「心霊写真(Shutter)」<2004年>、日本の映画祭で上映された「アンニョン! 君の名は(Hello
Stranger)」<2010年>や「フォウビア 2(Phobia 2)」<2009年>の中の「In The End」、「フォウビア(Phobia)」<2008年>の中の「The
Middle Man」、「アローン(Alone)」<2007年>などを手がけているホラー系の映像に力のある人だ。 |

[福岡アジア文化賞受賞記念上映&シンポジウム]
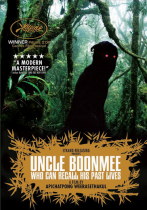 |
| 「ブンミおじさんの森」 |
| <上映されるタイ映画> |
| [邦題] |
ブンミおじさんの森 |
| [英題] |
Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives |
| [原題] |
ลุงบุญมีระลึกชาติ |
| [製作年] |
2010年 |
| [監督] |
アピチャーポーン・ウィーラセータクン<Apichatpong Weerasethakul/อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล> |
| [出演者] |
タナハット・サーイセイマー<Thanapat Saisaymar>、ジェンチラー・ホンパス<Jenjira Pongpas>、サックダー・ケァウブアディー<Sakda
Kaewbuadee>、ナッタカーン・アハイウォン<Natthakarn Aphaiwonk>、Geerasak Kulhong、Wallapa
Mongkolprasert、Kanokporn Tongaram、Sumit Suebsee、Samud Kugasang、Mathieu
Ly、Vien Pimdee |
2010年の第63回カンヌ国際映画祭で、タイ映画として初めてパルムドール(最高賞)に輝いて話題を博した作品。重い病にかかった主人公の中年男性が、亡くなった妻の幽霊や行方不明になり猿人となって戻ってきた息子と人生最後の時を過ごすという不思議なストーリー。この作品を監督したアピチャーポン・ウィーラセータクンは分かりにくい作品を撮ることでも有名だが、この作品も例にもれずほとんど理解できない内容となっている。
前半は変なストーリー展開であるもののなんとなくおもしろかったのだが、後半は展開が理解不能となり、ああ、いつものアピチャーポン監督の作品だという感じになってしまった。ラストの意味もまったく分からない。
行方不明であった息子は猿人になっていたのだが、説明がなければオオカミ男だと思うであろう容姿だ。僧侶が僧衣を脱ぐシーンがあるのだが、僧衣って中はああいう風になってるんだと分かっておもしろい。また、タイ人は誰でも知っているものだが、電池式のラケット型蚊取り器も登場する。もちろん場面説明はないので、あれって普通の日本人には何だかわからないであろう。なんでも僧侶が出てくるシーンが問題で、タイ国内ではカットするしないでもめたとか(結局、ノーカットで上映されたのだが)。原題は「ブンミーおじさん、人生を回想する」と訳すのか?
アピチャーポン監督の作品としては、他に山形国際ドキュメンタリー映画祭2001で優秀賞をとった「真昼の不思議な物体(Mysterious Object
at Noon)」<2000年>、2003年の東京国際映画祭に出品された「アドベンチャー・オブ・アイアン・プッシー(The Adventure
of Iron Pussy)」<2003年>、2004年度のカンヌ国際映画祭で審査員賞を受賞している「トロピカル・マラディー(Tropical
Malady )」<2004年>、「シンドロームズ・アンド・ア・センチュリー(Syndromes and a Century)」<2007年>などがある。 |

 |
| 「メコンホテル」 |
| <上映されるタイ映画> |
| [邦題] |
メコンホテル |
| [英題] |
Mekong Hotel |
| [原題] |
แม่โขงโฮเต็ล |
| [製作年] |
2012年 |
| [監督] |
アピチャーポーン・ウィーラセータクン<Apichatpong Weerasethakul/อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล> |
| [出演者] |
ジェンチラー・ホンパス<Jenjira Pongpas> |
ドラマ。場所はメコン川沿いの安ホテル。映画「エクスタシー・ガーデン」の撮影クルーが、そこでピー・ポープという霊(お化け)を題材にした映画の打ち合わせ&撮影?を行っている・・・というストーリー。
物語の舞台であるメコン川沿いの地は、イサーン(タイ東北部)のどこかなのだろうか?タイとラオスを結ぶ国際橋も映し出されていた。
映像的には魅力がないわけではないのだが、なにせストーリーというか中身が分からない。アピチャーポン監督の作品はどの作品も内容が分かりにくいが、この作品は特にそうだ。現実なのか幻想なのか?はたまた映画の構想なのか?分からない画面が、ギターの音色をバックに展開していく(このギター、静かで素朴な感じでなかなかいいです)。上映時間61分。ただとりとめもなく、ドキュメンタリー風のシーンが進んでいくだけだ。
ホテルの室内のベッド上で、ピー・ポープが女性の内臓を食らうシーンがある。悪いが、あれはただ女性のおなかの上に乗せてあるだけの腸に似せたソーセージ(ソーセージは腸だが)を食べているだけである。内臓を貪り食っているようには見えない。ホラー作品ではないので、そんな必要はないと言われればそれまでなのだが。また、ラストの夕日をバックにメコン川を我が物顔で走り回るジェット・スキーの長いシーンは何を言いたいのであろうか? |

| <上映されるタイ映画> |
| [邦題] |
アンセム |
| [英題] |
The Anthem |
| [原題] |
・・・ |
| [製作年] |
2006年 |
| [監督] |
アピチャーポーン・ウィーラセータクン<Apichatpong Weerasethakul/อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล> |
| [出演者] |
・・・ |
35mmで撮られた約5分の短編。内容は意味不明だ。アピチャーポーン監督の作品らしく、何を言いたいのかわからない。2013年、「アジアフォーカス 福岡国際映画祭
2013」で上映予定。
アピチャーポン監督の作品としては、第63回カンヌ国際映画祭でタイ映画として初めてパルムドール(最高賞)に輝いた「ブンミおじさんの森(Uncle
Boonmee Who Can Recall His Past Lives)」<2010年>、山形国際ドキュメンタリー映画祭2001で優秀賞をとった「真昼の不思議な物体(Mysterious
Object at Noon)」<2000年>、2003年の東京国際映画祭に出品された「アドベンチャー・オブ・アイアン・プッシー(The
Adventure of Iron Pussy)」<2003年>、2004年度のカンヌ国際映画祭で審査員賞を受賞している「トロピカル・マラディー(Tropical
Malady )」<2004年>や「アッシュズ(Ashes)」<2012年>、「モバイル・メン(Mobile Men)」<2008年>、「シンドロームズ・アンド・ア・センチュリー(Syndromes
and a Century)」<2007年>などがある。タイトルは「祝歌」「讃美歌」という意味だが、You Tube上の説明文に「Royal
Anthem」となっているので「国家」という意味も込めているのか? |

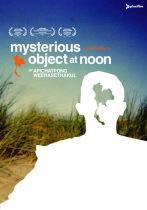 |
| 「真昼の不思議な物体)」 |
| <上映されるタイ映画> |
| [邦題] |
真昼の不思議な物体 |
| [英題] |
Mysterious Object at Noon |
| [原題] |
ดอกฟ้าในมือมาร |
| [製作年] |
2000年 |
| [監督] |
アピチャーポーン・ウィーラセータクン<Apichatpong Weerasethakul/อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล> |
| [出演者] |
Somsri Pinyopol、Duangjai Hiransri、To Hanudomlapr、Kannikar Narong、ประสงค์ กลิ่นบรม、สยมภู มุกดีพร้อม |
山形国際ドキュメンタリー映画祭2001の優秀賞受賞作品。その他、「JeonJu International Film Festival,
Korea, 2001」Grand Prix、「Vancouver International FF, Canada, 2000」Special
Mention Prizeを受賞している。
この作品の内容は何なのであろうか?ほとんど分からない。テーマは「先生は誰?」であろうか?「真昼の不思議な物体」とは何なのか?ちなみに、原題は「ドーク・ファー 悪魔の手元」。「ドーク・ファー」とは、作品中に登場する女教師の名前である。作品の前半はこの女教師を巡ってのストーリーがなんとなくあるのだが、後半はうわさ話を検証するようなインタビューが続きドキュメンタリー・タッチになってくる。見ていてこの作品がドキュメンタリーであるという認識はないのだが、山形国際ドキュメンタリー映画祭に出品されているのでドキュメンタリーなのか?いや、そんなはずはないだろう(製作会社のホームページによると、半分がフィクションで半分がドキュメンタリーとのこと。ということは、後半のインタビューがドキュメンタリーということだ)。
途中、第二次世界大戦当時のようなシーンは入ってくるし、ゴーゴーバーのシーンや手話、この映画の撮影合間の休憩シーンまで登場するというわけがわからない構成だ。最後の方のインタビューのようなシーンは、パンガー県のパンイー島で撮影されている。プーケットから007ジェームズ・ボンド島として知られているピンカン島へ行く多くのツアーで、途中、食事をするのがこの島だ。正確には、島というより水上集落だが。 |
|
 |

